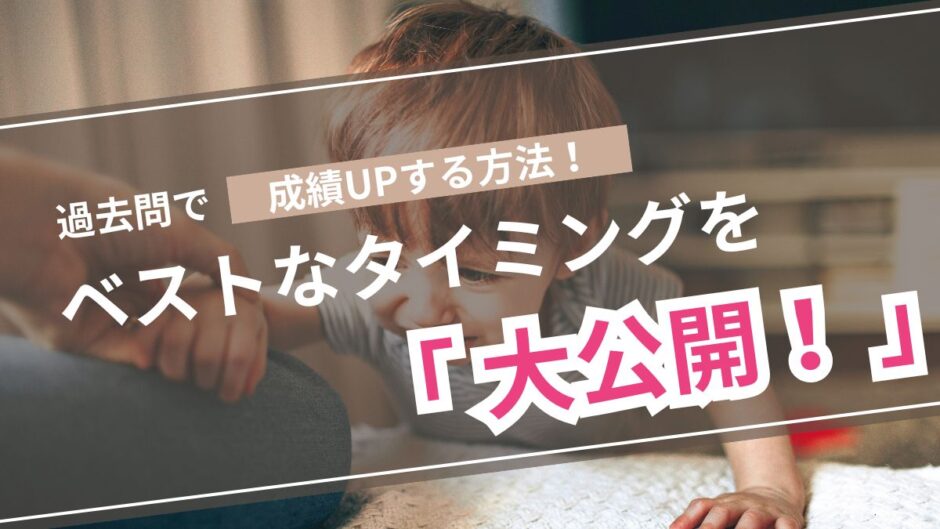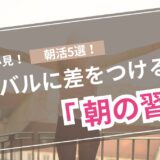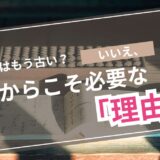※当サイトは上質な情報発信を続けてお役に立てるようサイト運営費用を賄う為に、Googleアドセンス・アフィリエイト等を利用しており本記事はプロモーションを含みます
📌 「まだ早い?」そう思っているうちに、ライバルはもう一歩前へ!
✅ 適切なタイミングで始めれば、合格力がぐんとアップ!
✅ ただ解くだけではNG!やり方次第で大きな差がつく!
✅ 「あと少しの努力で合格できたのに…」と後悔しないために、今やるべきこととは?
過去問を正しく活用すれば、今より 「+10点」「+20点」 も狙えるかもしれません。
でも、やり方を間違えると 「解いているのに成績が上がらない…」 なんてことも。
この差を生む「成功する過去問対策」とは? 今すぐチェック!👇
過去問を始めるタイミングはいつ?
中学受験を目指すご家庭では、「過去問はいつからやればいいの?」と悩む方も多いでしょう。
塾では 「6年生の9月からが目安」 と言われることが一般的ですが、これはすべてのお子さんに当てはまるわけではありません。
☑ 基礎が固まる前に始めると、自信を失ってしまうことも…
☑ 逆に、早すぎる段階で過去問をやっても「ただの答え合わせ」になりがち!
💡 過去問を解くベストなタイミングは、お子さんの「基礎学力の定着度」によって決まります!
そこで、今すぐチェック!👇
✅ 「このレベルなら過去問を始めてOK!」基準とは?
✅ 「過去問を解くと成績が伸びる」お子さんの特徴とは?
過去問を解く前に押さえておきたいポイント
「とりあえず過去問を解いてみよう!」という考えでは、なかなか効果が出ません。
過去問を最大限に活用するために、以下の3つのポイント を意識しましょう!
1️⃣ 基礎学力をしっかり固めてから取り組む
過去問は“試験のシミュレーション”のためのもの!
基礎が固まる前に取り組むと、解けない問題ばかりで逆効果になってしまいます。
✅ まずは、6年生の夏までは基礎固め&演習に集中!
✅ 「解くこと」よりも「理解すること」を優先!
💡 「基礎ができた!」と判断するポイントとは?
🔹 5年生までの範囲の計算問題・漢字をスムーズに解ける
🔹 苦手科目の克服がある程度できている
🔹 模試の結果で偏差値が安定している
2️⃣ 目標を設定し、進捗を管理する
過去問は「ただ解けばいい」ものではなく、戦略的に活用することが重要!
✅ 「1回目の正答率は○%を目標にしよう!」
✅ 「苦手な単元は何回か繰り返し解こう!」
✅ 「記録をつけながら、自分の成長を可視化しよう!」
☑ 過去問を解くときに、点数や正答率を記録しよう!
☑ 間違えた問題の原因を分析して、次につなげよう!
📌「できなかった問題こそ伸びしろ!」と考えれば、学習意欲もUP!
3️⃣ 時間配分を意識して訓練する
試験本番では、「制限時間内に解き切ること」が求められます。
過去問を解くときには、必ず時間を測りながら解く習慣をつけましょう!
✅ 「この問題には○分かけていい」と時間管理を意識!
✅ 苦手な問題は後回しにする判断力を身につける!
✅ タイマーを活用し、試験本番と同じ環境で練習!
「過去問は難しい…」子どものモチベーションを保つ方法
過去問に取り組み始めると、最初は**「思ったよりできない…」「点数が低くて落ち込む…」**ということもあるでしょう。
そんなとき、親がどのようにサポートするかがとても大切です!
ポジティブな声かけでやる気を引き出す!
✅ 「今はできなくても大丈夫!ここから伸びるよ!」
✅ 「1回目よりもできるようになったね!」
✅ 「間違えた問題こそ、今後の成長につながるよ!」
💡 「できなかったこと」に目を向けるのではなく、「成長したポイント」にフォーカス!
まとめ:過去問は「解くこと」より「活かすこと」が重要!
✅ 過去問は6年生の9月頃からが目安!でも、お子さんに合ったタイミングを見極めることが大切!
✅ 基礎が固まってから解くことで、学力アップにつながる!
✅ 目標を立てて進捗を管理しながら、効果的に活用!
✅ ポジティブな声かけで、やる気を引き出しながら取り組む!
🎯 正しく過去問を活用して、合格へ一直線!🌸
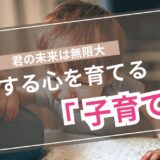 親がやりがちなNG行動とは?男の子をのびのび育てる方法
親がやりがちなNG行動とは?男の子をのびのび育てる方法